・俳人 ― 2016/09/14 15:46

俳人「尾崎放哉」の半生を書いた「海も暮れきる」を読んだ。読後感は暗く、強烈で、凄まじく、俳人というより廃人まっしぐらの最期という印象だ。
ノンフィクション作家の「吉村昭」は最も嫌いな作家の一人である。読みだすと次から次へと読みたくなるので、実は困る作家で津村節子には悪いが最も嫌いな作家なのである。
吉村昭の歴史小説は、史実に忠実であることが大きな特徴であり、この点については歴史学者も評価しているそうだ。作品を書くにあたり、史料・古文書を丹念に調べ、現地にも足を運ぶ。関係者にしっかりあたる。こうして、時には学者も知らなかった事実を発掘することもあるという。
こうした地道な作業に裏付けられているがゆえの面白さであり、作品の厚み、懐の深さなのである。
放哉は日本を代表する俳人の一人である。小説を読み進みながら、今更ではあるが俳句の歴史をおさらいしてみた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・俳句の歴史・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「古池や蛙飛びこむ水の音」
「閑さや岩にしみ入る蝉の声」
「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」

「菜の花や月は東に日は西に」
「春の海ひねもすのたりのたりかな」
「山は暮れて野は黄昏の薄かな」

「名月をとってくれろと泣く子かな」
「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」
「めでたさも中位なりおらが春」

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」
「いくたびも雪の深さを尋ねけり」
「牡丹画いて 絵の具は皿に 残りけり」
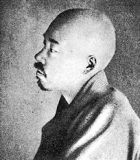
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
俳句革新運動「日本派」子規門下
「蛇逃げて我を見し眼の草に残る」

「曳かれる牛が辻でずっと見回した秋空だ」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(代表句)
・力一ぱいに泣く児と啼く鶏の朝
・たんぽぽたんぽぽ砂浜に春が目を開く
・うちの蝶としてとんでいるしばらく

(代表句)
・まっすぐな道でさみしい
・分け入つても分け入つても青い山
・うしろすがたのしぐれてゆくか
・どうしようもない私が歩いている
・酔うてこほろぎと寝ていたよ
・笠にとんぼをとまらせてあるく
・風の中おのれを責めつつ歩く
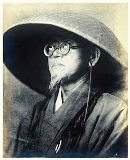
(代表句)
・咳をしても一人
・いれものがない両手でうける
・こんなよい月を一人で見て寝る
・足のうら洗えば白くなる

自由律俳句の代表的句者として、同じ荻原井泉水門下の種田山頭火と尾崎放哉は並び称される。山頭火、放哉ともに酒癖によって身を持ち崩し、漂泊・放浪の果て、師である井泉水や支持者の援助によって生計を立てていたところは似通っている。しかし、その作風は対照的で、「静」の放哉に対し山頭火の句は「動」である。
反面教師の二人だが、何故か気になるのである。誰もがそうはなりたくない、でも一度だけの人生、思い通りに生きるのもよさそうだと思うからだろうか。
放哉の最後の場面は、結核が悪化し気管支炎、喉頭結核を患っていたため、声も出ず、食べ物も水さえも飲めず、トイレにも行けず苦しみながら死んでいく場面である。死んだ時の姿は骨だらけで、その上に皮が覆っている骸骨同様で、その辺は吉村昭お得意の描写で真に迫り読むに耐えられない。
その頃に読んだ放哉の句が
「肉がやせてくる太い骨である 」 凄まじい創作意欲である。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。